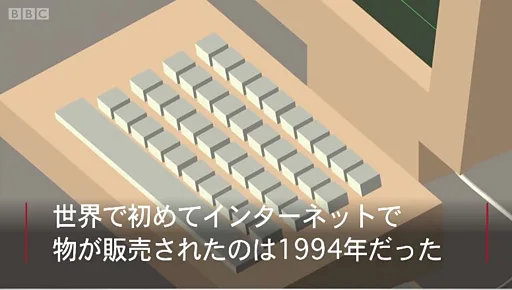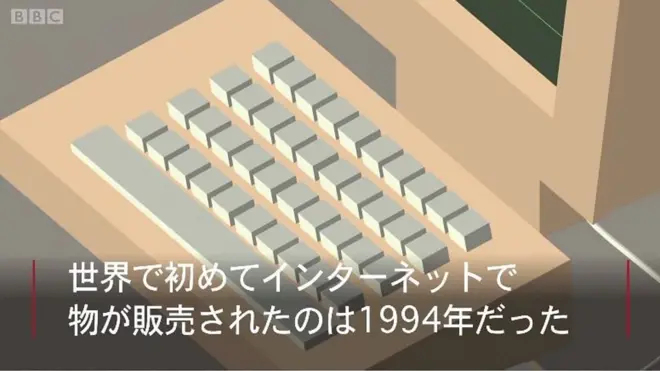世界を揺るがす――「何かお探しですか」 小売業の世界に激震
ルーシー・フッカー、スージー・ベアーン

リアルな世界の実店舗が、インターネットに反撃している。
バーチャル店員はその手段のひとつだ。モバイル・ショップの方から、あなたのところへやってくることだってある。
世界を揺るがす小売り改革で、私たちの買い物の仕方が変わるのだろうか。

1. お店が向こうからやってくる
夜遅くに終演したコンサート会場から流れ出てくる観客の波。その人ごみの中に自分もいたとする。へとへとで、おなかはぺこぺこだ。家には食べ物が何もないと思いだした。でも絶望しなくてもいい。
アプリのボタンをぽちっと押すだけで、小さい電気自動車が近くの駐車場に静かに到着する。見た目はまるで透明なキャンピングカーだ。
入り口でスマートフォンをかざして、この店の中に入る。必要なものを選んで、またスマホをかざして外に出る。レジ係も店員もいない。牛乳の箱を足に落としても、片付ける人はいない。
上海ではこの「モービー・マート」の試運転がすでに実際に行われた。未来の買い物の形を示す、ひとつの可能性だ。自動運転ソフトウェアはまだベータ版で実装に至っていないし、確実な運転を実現するには人の手が必要だった。
しかし、コンセプトとしては形になったと、開発チームは力説する。スウェーデンのベンチャー企業「ウィーリーズ」が、中国の合肥工業大学と提携して、この自動運転コンビニの開発に取り組んでいる。いずれは小売り大手から小規模コミュニティーに至るまで、誰もが自前の自動運転コンビニを使うようになるはずだと、開発チームは予想している。

「モービー・マート」のボー・ウー最高技術責任者は、世界が小売りの「大革命」の一歩手前にいると確信している。自動運転自動車、モバイル決済、データ分析、無線在庫管理など、既存技術の発展の方向性からすると、買い物経験を全面的に刷新するような、大きな可能性が待ち構えているというのだ。
「これで人のライフスタイルは変わると思うし、自分たちは世界を変えることになる」と、ウー氏は言う。
買い物というのは長いこと、街の中心部にあるチェーン店や百貨店、大規模ショッピングセンターでするものだったが、その勢いは減速しつつある。その一方で、新しい技術を取り入れた買い物の仕組みがいろいろと試されているが、いずれもまだかなりの初期段階にある。
自動運転の店舗が買い物客の指定する場所に無人でやって来る、あるいは自動で倉庫へ向かって在庫を補充するようになるまでには、超えなくてはならないハードルはたくさんある。無人運転自動車への規制がまず、その最たるものだ。
これまでのところ、2台の「モービー・マート」に買い手がついた。来年初めには、営業を開始する見通しだという。
その一方で、ほかにも新しい小売りの事業モデルが矢継ぎ早に登場している。いずれも、デジタル・テクノロジーの利点を現実世界に取り入れたものだ。
2. 人間味をプラス
かつて買い物というのは店に出かけて行って、ゆったり時間をかけてやるものだった。天気や人のうわさなどについてあれこれおしゃべりをしながら、店員が買い物の品を包んで袋に入れるのを待ち、そしてバスに乗って家に戻ったものだ。
シアーズやメイシーズといった米小売大手が一部の店舗を閉店するなど、小売店閉店のニュースは絶え間なく続く。しかしそれでも人は買い物をやめたわけではない(うわさ話も同様)。
しかしネット通販の台頭は、小売業界をひっくり返してしまった。便利で素早く、安くて、そして個々の客の好みに応えてくれるインターネットの買い物は、消費者の間でますます定着している。
アマゾンやアリババなどの世界的なネット通販大手は、驚異的なペースで客を獲得している。
とはいえ、それでも未だに、実際の店に出かけて買い物をするのが大好きだと言う人は多い。そのため(オンラインかどうかを問わず)小売業者は、実世界とデジタル世界の両方の長所を組み合わせて顧客に提供することが、最適解なのだと気づき始めている。
何よりアマゾンでさえ、リアルな実店舗の書店を数件開いたし、さらには全米460店舗の食品小売「ホールフーズ」を買収した。本物のレンガやしっくいでできた本物の店舗のチェーンを持つのは有意義なことだと、アマゾンでさえ判断したわけだ。ということはつまり、実店舗の時代は決して終わってなどいない。
そういう「お店」の形態が、全く見たことのないようなものに変わっていたとしても。
買い物には他人との接触がまったくいらない、そういう「買い物体験」の提供が未来の姿なのではないか。そう考えるのは、「モービー・マート」を作り出したチームに限らない。

画像提供, Getty Images
「ビンゴボックス」はすでに中国で150以上の固定無人店舗を運営し、今後数カ月の間でさらに数千店規模の拡大を予想している。個々の店舗は約10平米ほどの広さで、新鮮なサラダからコンドーム、ポテトチップスから傘に至るまで、幅広い商品を扱っている。
買い物客は入り口でスマートフォンをスワイプし、商品ごとにスキャンする。支払いはオンライン決済システムを使う。必要となれば、ビデオ・リンクでアシスタントとやりとりすることもできる。
要するにこの仕組みを使えば、わずかスタッフ4人で40店舗をきりもりできるのだと「ビンゴボックス」社は言う。かなりの経費削減になる。
今年7月には中国のオンライン小売最大手「アリババ」が、無人店舗を試験的にオープンした。「タオバオ(淘宝)」ブランドのポップアップ・カフェにはレジがなく、顔認識ソフトで入店する客を特定し、注文の品を選んでもらい、スマートフォンで支払う仕組みだった。

この「タオ(淘)カフェ」はアリババにとって、オンラインと実際の買い物体験を合体させるため、障害をどのように取り除き、費用をどう下げるかという実験だった。アリババ欧州ゼネラルマネージャーのテリー・フォン・ビブラ氏がBBCに説明した。
「タオ・カフェは、消費者にとってどれだけスムースな体験にできるか試す実験だった」
「中国では4億5000万人が私たちの決済アプリ『アリペイ』を使っている。これを手軽に活用するにはどうすればいいか。それほどの人数が同じスマートフォンのアプリをスムースに使っているというのは、素晴らしい土台となる。これを活用すれば、よその市場ではまだできないようなことが可能になる。中国ではそれができる」
そして実際、中国企業は世界に先駆けて、レジなし小売店鋪のコンセプト実現に突き進んでいる。
アマゾンは書店から家電まで、参入分野に相次ぎ革新をもたらしてきた。そのアマゾンが2006年12月には、シアトル本社の近くにレンガとしっくいでできた食品店「アマゾンGo」を試験的に開いた。
店員のいないこの店は、店内決済を省いている点でビンゴボックスのさらに先を行く。客は店に入り、スマートフォンをかざして到着したことを登録し、袋に商品をそのまま入れる。どの商品を選んだかはセンサーが読み取る。支払いは各自のアマゾン・アカウントを通じて、よどみなく行われる。
現在この店を使えるのはアマゾンの社員だけで、一般に公開する予定は発表されていない。

画像提供, David Ryder
「アマゾンはアマゾンGoの立ち上げに苦労した」 グローバルデータ・リテールの責任者、ニール・ソーンダース氏はこう言う。
「利用者が商品を棚に戻す動作を、センサーが正しく認識できなかった。店内の人数が多すぎると、システムがダウンして対応できなかった」
レジなし店舗の未来はそうそうたちまち実現するわけではない。しかし、いずれはその日がくるはずだとソーンダース氏は考えている。小売業者はオンライン店舗の低価格にどう競争したらいいか、方法をあれこれ模索しているからだ。とは言うものの、レジなし店舗は食品以外の分野にはあまり広がりそうにないというのが、ソーンダース氏の見方だ。
3. 「うわあ!」の要素
実際に出かけることのできるリアルな店舗と、オンライン限定の小売業者が競争するなか、リアル店舗にとって有利な競争の仕方はほかにもある。圧倒的に大多数の商品販売は今でも、実店舗で行われているのだし。
成功の決定打となるのは何と言っても、完全な小売りのエコシステムを作ってしまうことだ。データをもとに、消費者を熱心なクラブメンバーとして囲い込み、オンラインかオフラインかを問わず、一人一人のあらゆる気まぐれに応える総合的な買い物体験を提供するのだ。

アリババは「ヘマ(盒馬)」ブランドのキャッシュレス・スーパー13店舗で、この先駆的な戦略を展開している。店舗のほとんどは上海にある。創業者ジャック・マー氏は今年7月に店先を訪れ、楽しそうに水槽からカニを取り出してみせた。
鮮魚をその場で選ぶことができるなどの体験を提供することで、「ヘマ」スーパーは顧客を実店舗に誘い込もうとしている。商品棚のバーコードをスキャンすれば、商品の生産地など関連情報を手元の電話に取り込むこともできる。この技術は他の先駆的な小売業者にも活用されている。
ポイントとなるのは、選択の幅だ。生きたカニを水槽から選んだら、「ヘマ」レストランのシェフに調理してもらうこともできるし、そのまま持ち帰ることもできる。自宅から食料品を、あるいは調理済みの料理を注文し、自分で取りに行ってもいいし、配達してもらってもいい。注文も支払いもすべて、共通のオンライン「ヘマ」アカウントで行う。
実に幅広い選択肢を提供することで、利用者は食事に関するすべてを「ヘマ」のプラットフォーム内で済ませられるようになる。それが同社の狙いだ。利用者はこのコンセプトを歓迎しているという「ヘマ」は言う。しかし利益は出るのだろうか。
「もちろんです」と、テリー・フォン・ビブラ氏は言う。「中国のような市場では、上手に場所を選べば店舗の3キロ圏内に膨大な数の消費者がいる。その人たちの要求にきちんと応えれば、大繁盛だ。実際にそういう結果につながっている」。

実店舗での買い物とオンラインの買い物の体験を一体化しようとしているのは、複数の大陸で展開するフランスの化粧品チェーン「セフォラ」も同様だ。
「業界全体がデジタル化しているので、みんな対応しなくてはならないし、実際の店舗での経験をより豊かなものにするには絶好の機会です」と、ステファーヌ・デルバ氏は言う。セフォラの欧州・中東マーケティングを統括するデルバ氏は、客が「うわあ!」となる体験を充実させるために新しい技術を活用しているのだと話す。
iPadで拡張現実ソフトウェアを使うと、客は色々な色のチークやアイシャドウや口紅を試すことができる。納得のいくまで試した上で、アプリ上で写真を撮って、ソーシャルメディアで共有する。試した商品を巨大なタッチスクリーンで注文すると、自宅まで届けてもらえる。
ある意味でこの方法は若者がすでにオンラインでやっていることを、後追いしているに過ぎない。若者はとっくに、メイクアプリやオンラインのヘアメイク・レッスンを活用し、チャットルームで情報交換をして、自分の最新ルックをスナップチャットなどで共有しているのだ。
しかしリアルな世界に足場を置く小売業者にしては、非常に優れて包括的な取り組みだ。利用客は「マイ・セフォラ」のデジタル・コミュニティーに参加するよう促される。会社はそこで、顧客が何を買い、何を話題にして、何が好きなのかを把握できる。大量の有用な情報が手に入るというわけだ。
「最適な商品を提案して、アドバイスができるよう、顧客の購買履歴を集めている」とデルバ氏は言う。
「これまでの成果に非常に満足している。個人向けの商品提案ツールを実装したのは、弊社が初めてだった」
オンラインとオフラインの買い物体験をつなぐサービスを提供する「セフォラ」店舗は、まだ限られている。オンラインとアプリ上の拡張現実体験はまだ、実際の店舗でのお試し体験に比べるとタイミングがずれるし、本来ならスムースな買い物体験でなくてはならないはずのものが、技術的なバグで滞ることもある。
しかしこの販売戦略を展開するに伴い、セフォラはパリに拠点を置くITスタートアップ各社と提携し、この分野につきものの急速な技術革新に歩調を合わせていくつもりだと、デルバ氏は言う。
4. 値段、値段、値段
最先端の技術がどれほどキラキラまばゆくても、無視しないに越したことのない最後の関門がある。
近年の小売市場を何より大きく揺さぶってきたのは、スマートフォンのスワイプ技術でもデータ高速処理でもなく、昔ながらの価格競争だ。いかにライバルより安く売るかという、おなじみの戦術だ。
ドイツの格安小売り大手アルディやリドルは、余計なものを一切排した基本的なサービスを提供しながら、品揃えを食料品以外にもどんどん変化させている。思わぬものが格安で買えるので、ちょっとした宝くじ気分を味わえることもある。
欧州の伝統的な食品小売業界に打撃を与えるだけでは飽き足らず、リドルは最近、米国市場にも進出した。今年に入りこれまでに21店舗を開くことで、すでに1600店舗を展開しているアルディの仲間入りを果たした。
「製品や売り場のレイアウト、建物そのものについて、かなり米国市場向けの調整をしました」と、米リドルの広報担当、ウィル・ハーウッド氏は話す。
「けれども結局のところ、ベストな値段で最高の品質を提供するというのがリドルの基本なので、ここのお客さんにも同じようにそれを提供できて、本当にわくわくしている」

米国の食料品業界はただでさえ、アマゾンとホールフーズの合体に震えている。ウォルマートもつい最近、グーグルと提携して音声対応型の買い物方式を導入すると発表した。格安小売り大手が、デジタル技術に頼らない単純な買い物体験を提供すれば、競争圧力はさらに高まる。
「リドルはかなり市場を揺さぶることになると思われている」 テルシー・アドバイザリー・グループの調査担当、ジョー・フェルドマン氏はこう言う。
とは言うものの、リドルの前に立ちはだかるものは巨大だ。進出への期待は高かったものの、米国では未だにごく小さな存在にすぎない。そして、既存の食品小売り業者は、この新たな競合の到来に強く対抗している。
米国の消費者は今のところ、ハインツやモンデレズなどおなじみのブランドの商品に強くこだわっている。そうした愛着心あふれる米国の消費者をリドルが説得して、もっと安い自社ブランドに引きつけられるかどうか。しかも費用を抑えながら。これが、リドル進出戦略の鍵となる。
フェルドマン氏によると、商品の材料を自社でコントロールし、大量注文による規模の経済の優位性を活用することで、リドルは自社ブランド商品の価格を低く抑えられる。さらに、できる限り費用を削減してくるはずだ。
「非常に効率の良い事業で、それほど人手を必要としない店舗もある。米国のスーパーに比べて、店内サービスはそれほどないし、従来の食品小売店と比べてレジの支払いもかなり簡素化されている。その結果、価格を全体的に抑制できるというわけだ」
ただし、フェルドマン氏いわく、ほかのことはともかく、リドルは人間のレジ係を一掃はしないだろう。
「誰かに『ケチャップはどこ?』とか『からしはどこ?』と聞く客は、ずっといなくならないと思うので」

(DXCテクノロジーと共同企画記事)
記者:ルーシー・フッカー、スージー・ベアーン
ビデオ製作:エイドリアン・マリー
ビデオ編集:サラ・ヘガティー
シリーズ・プロデューサー:フィリパ・グッドリッチ
ショートハンド製作:ハープーン・プロダクションズ
編集:ロブ・スティーブンソン
制作責任:メアリー・ウィルキンソン
プロダクション・チーム:
- 中国――マーク・ダムール、ジャスミン・グー、カーティス・ロッダ、ヤン・チュオ
- フランス――グレッグ・ブロスナン
- 米国――アレン・マクグリービー、モーガン・ジショルト・ミナード
グラフィック・アーティスト:スー・ブリッジ
画像提供:ゲティ、アリババ、BBC、リドル、アマゾン
<BBC「世界を揺るがす」シリーズ 世界を揺るがす――新しい宇宙競争>