がれきの下から姉妹が救助されるまで……トルコ南部アンタキヤ
ナフィセ・コーハバルド中東特派員(トルコ・アンタキヤ)、BBCペルシャ語
「メルヴェ! イレム! メルヴェ! イレム!」と、救助隊員のムスタファ・オズトゥルクさんは叫んだ。周囲にいた人たちは静かにするよう命じられた。救助チームは、がれきの下に閉じ込められているという2人の姉妹を探している。他の生存者が、そう証言したのだ。
高感度センサーを使いながら、反応を待った。みんなが期待しながら固唾(かたず)を飲んで、じっとしていた。
そして、ムスタファさんが声を上げた。
「イレムさん、近くにいるよ、聞こえる?」
見守っていた私たちには聞こえなかったが、イレムさんが反応していることは明らかだった。姉妹の友人たち数人も、私たちと共に静かに待っていた。
「すごいぞ! さあ落ち着いて質問に答えて。ああ、メルヴェだね、メルヴェさん、私の質問に答えて」と、ムスタファさんが話しかけた。
メルヴェさん(24)とイレムさん(19)姉妹は、トルコ南部アンタキヤで、地震によって崩れた5階建ての集合住宅の下敷きになった。地震発生から2人が助け出されるまで2日かかったが、2人には何週間にも感じられたようだ。
「今日は水曜だ、14日も閉じ込められていないよ! あと5分で外に出られるから」
ムスタファさんは、救助には5分ではなく何時間もかかると分かっていたが、「希望を失えば2人は生き残れないかもしれない」と、私たちに話した。

メルヴェさんとイレムさんは冗談を言い合い、笑い始めた。ムスタファさんも大きな笑顔を浮かべた。「空間があれば2人とも踊っていたはずだ」。
救助隊の計算では、2人の場所まで2メートルあった。しかし隊長のハサン・ビナイさんは、コンクリートに穴をあける作業はとても繊細な作業だと話す。一歩間違えば大惨事につながる。
掘削作業が始まる際には、建物が崩れないよう分厚いコンクリートを支えるため、ブルドーザーが出動した。
「もうすぐ毛布を渡すから」と、ムスタファさんが姉妹に話しかけた。「私たちのことは心配しないで、疲れていないし、寒くもないから」。
ムスタファさんによると、メルヴェさんは救助隊のことを心配していた。その時点で時計は午後8時半を回っており、とても寒かった。この地域は記録的な寒さに見舞われていた。
救助隊は熱心にがれきを掘り始め。素手で破片を放り投げた。
しかし数時間後、突然地面が揺れだした。強い余震だった。作業は中断され、我々は危険な建物を離れた。
「残酷な現実だが、救助隊の安全が第一だ」と、ハサンさんは話した。
「怖がらないで、置いていかないから信じてほしい。ここから出してあげるから、そのうちおいしいランチをおごってね」と、ムスタファさんは叫んだ。メルヴェさんとイレムさんは、置き去りにされて死ぬのだと思っていた。

真夜中を過ぎて、作業は再開された。救助隊はもう何日間もほとんど寝ていなかった。我々は建物の隣に小さな火をたいて集まった。
何度も何度も、「静かに!」という怒鳴り声があがった。光が消され、真っ暗になった。コンクリートに開けた小さな穴から、姉妹がムスタファさんの持つ懐中電灯の光が見えるかを試しているのだ。
「メルヴェ、イレム! この光が見えるか? よし、完璧だ! 今から小さなカメラを送るから、見えたら教えてほしい。やり方を説明するから」
<関連記事>
全員の表情が明るくなった瞬間だった。ハサンさんもチームに加わり、暗視カメラに接続された小さなスクリーンで姉妹を確認した。メルヴェんもイレムさんも、そこにいた。
「本当にきれいだ。あまり動かないで。イレム、カメラを引っ張って。そうすれば、メルヴェのこともよく見える」
スクリーンの中で、イレムさんは笑っていた。幸運なことに、2人が閉じ込められているコンクリートには十分な空間があった。
全員の顔に安堵(あんど)が広がった。2人とも異常はなさそうで、少なくともイレムさんは、穴を広げれば自力で抜け出せそうだった。
しかしすぐに、救助隊に不安がよぎった。メルヴェさんが寒気がしてきたことと、足に何か重いものが乗っていると訴えたのだ。
医師は、「足に壊疽(えそ)があるのか? それとも低体温症の初期症状か?」と心配していた。
朝5時になっていた。トンネルは、細身の救助隊員が降りられるほどの大きさになった。救助隊員は2人に近づき、イレムさんの手をしばし握った。
イレムさんは、「死んだお母さんの身体がにおい始めて、うまく呼吸できない」と話した。2人はこの数日間、亡くなった母親の遺体の隣に横たわっていた。
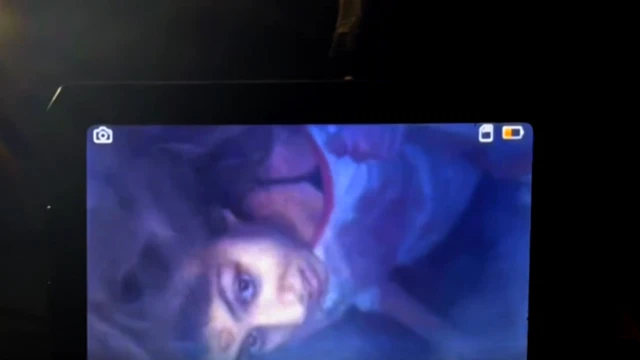
衝撃だった。母親が隣にいるのが困ると思うような瞬間が、生きていてあり得るとは。
ハサンさんは、ストレスにさらされながらも静かに待っていたメルヴェさんの友人の1人に、2人の写っている写真を見せてくれないかと尋ねた。必要な穴の横幅を計算する必要があったからだ。友人の写真では、2人がパーティードレスに身を包み、結婚を祝って微笑んでいた。
「完璧だ! 2人を助けられる」。医療チームは発熱毛布とストレッチャーを準備した。みなが興奮していた。午前6時半、まずはイレムさんが外に出た。イレムさんは泣き笑いしていた。
「神様のお恵みがありますように。メルヴェも出してあげて、お願い」と、イレムさんは救助隊に言った。ハサンさんは、「メルヴェも来る、約束する」と答えた。
しかしメルヴェさん救出までには、さらに緊張の30分がかかった。メルヴェさん自身を傷つけないよう、コンクリートの下から彼女を足を抜き出す必要があったからだ。この作業は成功した。
メルヴェさんが外に出ると、全員から拍手と喝さいが起こった。メルヴェんが、痛みにうめきながら「私生きてる?」と尋ねているのが聞こえた。
「もちろんだ」と、ムスタファさんが笑顔で答えた。
夜通し2人を待っていた友人たちも、涙を流しながら叫んだ。「メルヴェ! イレム! 私たちがここにいるから! 怖くないよ!」。
姉妹は救急車に乗せられ、臨時病院に搬送された。
喜びの時間の後には、厳しい時間が待っている。救助隊はみなに静かにするよう告げた。これが最後の呼びかけだ。
「この声が聞こえたら答えてください。声が出せないなら、地面に触れてみてください」
ハサンさんは繰り返し、切実な声で、色々な方角から呼びかけた。その後、残念ながら、ハサンさんは赤いスプレーでコンクリートにコードを記した。救助隊はこの建物をもう捜索しないという印だ。
「人命を助けられると素晴らしい気持ちになる。でも、誰にも死んでほしくない」。そう言うハサンさんは悲しそうだった。
「メルヴェさんイレムさんとお昼ご飯を食べるんですか?」と聞くと、ハサンさんは微笑んだ。「いつかそうできれば。でも一番重要なのは、2人が生きていて、しっかりした手当を受けられるようになったことだ」。










